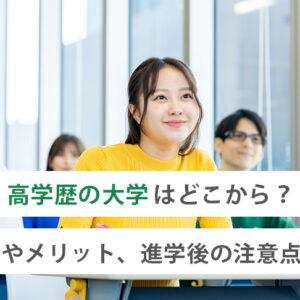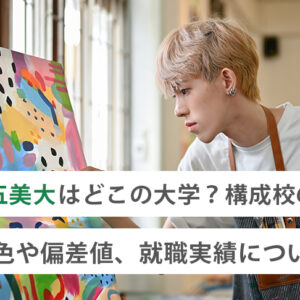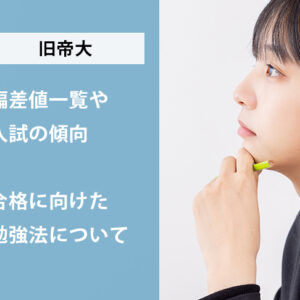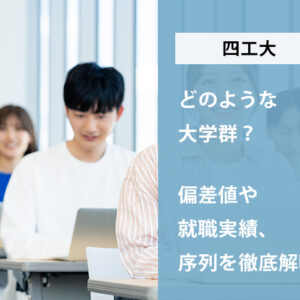東京大学(以下、東大)と早稲田大学(以下、早稲田)はいずれも偏差値が高く、全国でもトップクラスの学力を誇る大学です。どちらの大学を受験しようか悩んでいる人は、大学の教育方針や特色を理解したうえで、自身の価値観に合う大学を選びましょう。
本記事では、東大と早稲田のどっちが難しいのか、偏差値や入試傾向を比較しながら紹介します。東大と早稲田がおすすめの人の特徴についても解説するので、難関大学の受験を検討している高校生・浪人生は参考にしてください。
東大と早稲田の概要

下表を見ると、マンモス大学といわれる早稲田は、学部学生数やキャンパスの数が東大よりも多いことがわかります。
| 東京大学 | 早稲田大学 | |
| 学部学生数 | 14,058人 | 38,987人 |
| 学部 | 法学部、工学部、文学部、理学部、農学部、経済学部、教養学部、教育学部、薬学部、医学部 | 法学部、政治経済学部、教育学部、国際教養学部、商学部、社会科学部、文化構想学部、文学部、人間科学部、スポーツ科学部、先進理工学部、基幹理工学部、創造理工学部 |
| キャンパス | 本郷地区キャンパス、駒場地区キャンパス、柏地区キャンパス、白金台キャンパス、中野キャンパス | 早稲田キャンパス、東伏見キャンパス、戸山キャンパス、西早稲田キャンパス、所沢キャンパス、喜久井町キャンパス、日本橋キャンパス、北九州キャンパス、本庄キャンパス |
| 創立年 | 1877年 | 1875年 |
※2024年5月時点
以下では、各大学の特色について詳しく見ていきましょう。
東大とは
東大は、10の学部で教育を行う総合大学です。1877年に東京医学校と東京開成学校が合併し、東大が設立されました。ノーベル賞の受賞者を始めとした、数多くの著名人を輩出しています。
東大では「リベラルアーツ教育」と呼ばれる教育カリキュラムを推進しています。特定の分野にとどまらず、幅広い領域の学問を偏りなく学べる点が特徴です。
入学後の2年間は、学部生の全員が教養学部へ所属します。学生の希望や前期課程の成績に応じて、3年次で所属する学部が決定するため、2年間かけて自身が学びたいことを慎重に選ぶことが可能です。
早稲田とは
早稲田は、都内をメインに9つのキャンパスを擁する、国内でトップクラスの難関私立大学です。創立150周年となる2032年に向けて、国際社会でリーダーシップを発揮できる人材の育成や、進化を繰り返しながら世界的に信頼される大学を目指しています。
全学部生が履修できる科目が多数用意されており、総合大学ならではの規模で幅広い分野を学べる点が特徴です。「全学オープン科目」では、学術的文書の作成やプログラミングなど、あらゆる学問の基礎となるスキルを習得できます。
【偏差値比較】東大と早稲田はどっちが難しい?

以下では、東大と早稲田のどっちが難しいのかについて、「偏差値」を基に確認していきましょう。
東大と早稲田の文系偏差値
下表では、東大と早稲田の文系学部における偏差値をまとめています。
| 大学 | 偏差値 |
| 東京大学 | 文科一類 67.5 文科二類 67.5 文科三類 67.5 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 67.5~70.0 法学部 67.5 教育学部 62.5~67.5 商学部 65.0~67.5 社会科学部 67.5~70.0 国際教養学部 70.0 文化構想学部 65.0~70.0 文学部 67.5~70.0 人間科学部 62.5~65.0 スポーツ科学部 62.5~65.0 |
※2025年1月時点
東大はどの科類も偏差値67.5であり、一貫して難易度が高いことがわかります。一方で、早稲田は学部間の偏差値差が大きい点が特徴です。
そのため、東大と早稲田のどちらが難しいかは、学部によって異なるといえます。
東大と早稲田の理系偏差値
下表では、東大と早稲田の理系学部における偏差値をまとめています。
| 大学 | 偏差値 |
| 東京大学 | 理科一類 67.5 理科二類 67.5 理科三類 72.5 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 65.0 創造理工学部 62.5~65.0 先進理工学部 65.0~67.5 |
※2025年1月時点
上表を見ると、東大と早稲田の理系科類・学部を比較した場合、東大のほうが難しいことがわかります。
【倍率・傾向比較】東大と早稲田はどっちが難しい?

偏差値だけでなく、「倍率」や「入試傾向」も難易度を知るための指標となります。以下では、東大と早稲田の倍率や入試の特徴を紹介します。
東大と早稲田の倍率
以下は、東大と早稲田の倍率を比較した表です。
| 大学 | 倍率 |
| 東京大学 | 2023年 2.8 2024年 2.8 |
| 早稲田大学 | 2023年 5.4 2024年 5.2 |
※大学計
過去2年間の倍率を見ると、早稲田のほうが東大よりも倍率が高くなっています。競争率から判断すると、早稲田の難易度が高いといえるでしょう。
東大の入試傾向
東大の入試は、出題範囲が広いため膨大な知識が必要です。そのため、学校の授業で使用する教科書レベルの問題は完璧にしておく必要があります。入試傾向として、試験時間に対して設問数が多いため、スピーディーかつ的確に解答しなくてはなりません。なお、基本レベルの問題が出題される傾向があるので、応用よりも基礎を優先しましょう。
英語は多彩な形式の問題が登場し、英文作成力・リスニング力・読解力など、総合的な知識が必要です。隙間時間を活用しながら、各分野を満遍なく勉強するようにしてください。教科書をメインに活用し、インプットとアウトプットをバランスよく取り入れながら知識を定着させることが大切です。
早稲田の入試傾向
早稲田の入試は、全体的に問題の難易度が高いうえに、制限時間内の解答が難しいといわれています。英語の長文ではマニアックなテーマから出題され、専門用語に関する知識も求められます。ハイレベルの単語帳を活用し、速読力も身につけるようにしましょう。
教科書には載っていない分野からも出題され、難易度でいうと東大を上回るといわれています。そのため、日本史・世界史であれば歴史の流れを網羅し、地理であれば国の位置関係をしっかりと覚えましょう。日頃から新聞に目を通し、政治経済の時事問題や現代文の長文問題に対応できるようにしてください。
東大と早稲田のどっちがおすすめ?

以下では、東大と早稲田がおすすめの人の特徴を解説します。
東大がおすすめの人
大学で学びたいことがまだ決まっていない人は、東大への受験がおすすめです。東大には進学選択制度があり、入学後の2年間は学びたい分野を見定められます。高校の文理選択で、数学や理科などの理系科目が苦手だと感じたことをきっかけに、文系を志望した人もいるでしょう。文科一類に入学した場合でも、工学部や理学部などの理系学部に進学できる可能性があります。
また、東大は国公立大学であるため、私立大学の早稲田と比べると学費が安い点がメリットです。金銭面での負担を減らしたい人にも、東大が向いているといえるでしょう。
早稲田がおすすめの人
英語力を養いたい人は、早稲田がおすすめです。国際教養学部は英語で授業を進行し、1年間の留学が必須となっています。また、早稲田の留学センターは、短期留学科目やサマーセッション科目などを提供しており、授業を通じて異文化体験や外国語学習が可能です。
サークル活動にも熱心に取り組みたい人も、早稲田が向いています。早稲田には3,000近くのサークルがあるといわれており、他学年の人々と交流する機会が豊富に用意されています。
また、スポーツが盛んな大学を選びたい人も早稲田がおすすめです。早稲田アリーナをはじめとする運動施設が完備されており、天候に左右されることなくさまざまなスポーツを楽しめます。
まとめ
入試の難易度でいうと、東大よりも早稲田のほうが難しいといわれています。大学選びの際は、難易度のみで判断するのではなく、自身の関心や価値観に基づいて検討しましょう。
なお、東大と早稲田は、どっちも偏差値60~70台とレベルが非常に高い大学です。合格を目指すには、各大学の入試傾向に合わせた入念な対策が欠かせません。効率よく受験勉強を進めたい人は、予備校や塾への通学をおすすめします。塾・予備校を探している高校生・浪人生は「イチオシ予備校一覧ページ」をチェックしてみてください。
自分に合った学習スタイルは見えてきただろうか?
具体的に予備校を比較してみよう